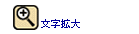

・ ・・会のメンバーはジャーナリスト・保健婦・新聞記者・養護学校の教員や福祉施設の職員・・・と多彩な顔ぶれですね。どうやって集められたんですか?
僕は「ベトちゃんとドクちゃんの発達を願う会」の事務局長をやってるんです。僕の自宅が全国事務局なんで、マスコミ関係者が年がら年中やって来るという状態でした。一方で、障害をもっている人たちや大学生がボランティアで来たりと、いろんな人たちが集まってくる下地があったんですね。そこで「障害者の性に関心はないか?」と声をかけたら、あっという間に15人ぐらい集まったというわけです。
・ ・・なるほど。
研究会を立ち上げたとたんに出版社から編集者がやって来て、「本を出す前提で研究会を構成してくれませんか」と言われまして。それで、翌日から活動を始めた・・・ということです。
おおらかに育った自分は珍しい存在だった
・ ・・河原さんご自身は、もともと性というテーマに関心をもっていたんですか?
僕は20代の頃から「全障研(全国障害者問題研究会)のエッチな兄ちゃん」で通っていまして(笑)。というのも、全障研の全国大会で性について初めてしゃべったうちの一人なんです。
 ・・・そんな河原さんがどう育ってこられたのか、興味があります。どんな子ども時代や思春期を過ごされたんですか?
・・・そんな河原さんがどう育ってこられたのか、興味があります。どんな子ども時代や思春期を過ごされたんですか?
僕は4歳から17年間、病院と施設を転々としていたんです。だから大人のなかで育ったヘンな子どもだったんですけど(笑)。しかし幸いなことに、ドクターを始め「いい大人」たちに育てられてね。偏見や差別にさらされたり、「障害者」ということをあまり意識させられることもなく、ずぼら・気ままに過ごしてきたところがあるんですよ。
・ ・・じゃあ、性についてもおおらかに?
ええ。たとえばある大学病院にいた時。今から40年ほど前の話ですから、完全看護ではなくて母が付き添ってくれていたんです。ところが母は体がすごく弱くて、時々倒れるんですよ。でも付き添い婦さんはすぐには間に合わない。そこで婦長が、付属の看護学院から実習にきている学生に「正実ちゃんを連れて帰ってよ」と言うわけです。
これがいいんですよ〜(笑)。お風呂に入れてくれたうえに、抱っこしてもらって一緒に寝るんです。その時に「固い乳房」というのを初めて知ったんです。そのおっぱいは母のより遥かによかった。だから僕はあの頃、いつも考えてましたね。「母が早く倒れないかなあ」って(笑)。いい時代でしたねえ。今はもう病院も管理主義が徹底していて、あんなことは夢にも考えられませんけど。まあ、こんな調子ですごくオープンな状態で少年期を過ごせたんです。
・ ・・それは確かにいい時代でしたねえ(笑)。夢精やマスターベーションを覚える時期はいかがでしたか?
実習にきている学生さんは、当時の僕にとっては看護婦というよりもお姉さんという感覚だから、何でも聞いたんですよ。それで夢精もマスターベーションも教えてもらって、手伝ってもらいました。そういう意味では非常に早熟でしたし、ヘンな抑圧もなかった。
研究会を始めてから、下着を汚したりすると叩かれたり、夢精をガンだと思い込んで遺書を書いたり・・・それも30代40代の人が、ですよ。そんなことが珍しくないということを初めて知ったんです。僕は自分とのあまりのギャップに驚いたし、周りは周りで僕の話を珍しがった。そんなところから研究会が始まったんです。


