|
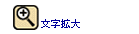

横浜中華街のほど近く、JR石川町からぶらぶらと10分ほど歩けば寿町だ。赤いちょうちんやのれんを下げたちいさな店が軒を並べ、作業着やニッカボッカ姿の男性たちが三々五々歩いている。この高層ビルに囲まれた300メートル四方のドヤ(簡易宿泊所)街に、6500人ほどが住む。高度経済成長期やバブル時代には活気がみなぎっていたが、今は高齢化と不景気の長期化によって9割近くの人が生活保護を受給しているという。
寿識字学校が開かれるのは、保育所や学童保育、日雇い労働の人たちが利用するシャワーや洗濯機、娯楽室が入っている寿生活館だ。築30年はゆうに過ぎた建物の階段を4階まで上がる。1970年代にはオイル・ショックで仕事がなくなった労働者が布団をもちこんで泊り込み、当時の横浜市長が機動隊を差し向けたという歴史をもつが、今は人影もまばらだ。
「教室」となる会議室は長い机がコの字型に並び、お互いの顔が見える。大沢さんは手早く、けれどていねいに机を拭き、鉛筆や資料を並べ、ポットにお湯を入れてお茶の準備をした。ここ数年、寿町の高齢化に合わせるように参加者はジワジワと減ってきている。今日、もしかすると誰も来ないかもしれない。それでもいい。けれど誰かが来た時は温かいお茶で歓迎し、ツンと芯のとがった鉛筆で思うがままに文字を書いてほしい。そんな気持ちが伝わってきた。部屋の準備が整うと、大沢さんは「寿識字学校(「ことぶきしきじがっこう」とルビをふってある)」と書かれた手書きの小さな「看板」を入口に掲げた。隣りの娯楽室からボリュームを上げたテレビの音声と、それに張り合うかのような男の人の声が聞こえてくる。一瞬、「ケンカ?」と思ったが、そうではないようだ。大沢さんが淹れてくれた熱いお茶を飲みながら、識字学校が始まった。

――識字って何だろう、文字の読み書きができないってどういうことだろうと考えました。生活のなかの「読み書き」を改めて見直してみると、息をするのと同じぐらい、ほとんど無意識にさまざまな場面で読み書きをしていることに気づきました。新聞に挟み込まれているチラシや回覧板、買い物した時のレシート、電車やバスの運賃表や時刻表、病院にかかった時に書く問診表…。「知識」や「教養」のためじゃなく、生活するために欠かせないものです。もし、これらが読み取れなかったり伝えたいことがきちんと書けなかったりしたら、ものすごく不安です。
 寿町で簡易宿泊所を経営している在日朝鮮人一世の金 孟任(キム・メンニム)さんという女性がいます。ある時、彼女に姜 舜(かん・すん)という詩人の「蛇口」という詩を紹介したことがありました。いわゆる朝鮮人部落の1本しかない水道の蛇口に、たくさんの長屋の人たちの生活がつながっているという内容の長い詩です。すると金さんはとても感動するんです。「“蛇口”とは、こういう字を書くんですか!」と。 寿町で簡易宿泊所を経営している在日朝鮮人一世の金 孟任(キム・メンニム)さんという女性がいます。ある時、彼女に姜 舜(かん・すん)という詩人の「蛇口」という詩を紹介したことがありました。いわゆる朝鮮人部落の1本しかない水道の蛇口に、たくさんの長屋の人たちの生活がつながっているという内容の長い詩です。すると金さんはとても感動するんです。「“蛇口”とは、こういう字を書くんですか!」と。
たったひとつの蛇口で大勢が生活していたという実感はあるけれど、「じゃぐち」がどんな字なのかを知らなかったわけです。何十年も「じゃぐち」と口にしながら、どう書くのかを知らなかったという事実。そして毎日使っている「じゃぐち」と「蛇口」という文字が重なった時の感動。金さんの反応に、改めて被差別の重みと識字の何たるかを感じました。
識字とは、ただ「読み書き」を学ぶということではありません。字を覚えることによって自分のなかにあるさまざまなことを表現する。小学1年生がひらがなを習うようではなく、生きてきたことのなかから言葉を生み出していくのです。たとえ内容は「今日は何をした」というものであったとしても、そこには、その人の生きてきた長い生活の歴史があります。小学1年生が書く文章とはきっと違うはずです。
――「文字の読み書きができる」ことと、「文章を書く」ということは違うのですね。
そうです。識字は教育とか(差別からの)解放の原点だと言われています。なぜ、子ども時代に学校へ行けなかったのかというと、そこに「差別」があったからです。なかには「学校へ行かなかったから差別に遭わなかった」という人もいますが、部落差別や朝鮮人差別に遭って学校へ「行けなくなってしまった」という人が圧倒的に多いのです。学校へ行けなくなってしまった「中身」や、それから苦労して20年30年と生きてきた道のりをあきらかにすることが本来の識字だとぼくは考えています。
そしてあきらかにする部分というのは、被差別の文化だと思うんですね。寿識字学校がすべてだとか素晴らしいとは言いませんが、ここで書かれる文章にいつも圧倒されます。
|


