|
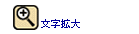

自ら命を絶つ人が6年連続で3万人を越えている。自殺を考える人の大半が抱えているという心の病。その多くが「うつ病」とされ、本人や周囲の人が少しでも早くうつ病に気づき、適切な治療を受けることができれば、自殺防止へつながっていくといわれている。その「うつ病」の実態とは? 自らうつ病に苦しみ、精神医療の問題に取り組んできた山本深雪さんにお話を伺った。
■うつ病とは脳の疲労による病気■
やる気が出ない、眠れない、疲れやすいなど無気力な状態が長期間続き、将来に希望がもてないばかりか、過去の自分に罪悪感をいだくようになる。憂うつ感とともに、これまで好きだったことにも興味や関心を失い、意欲も低下する。しかも、心の不調だけでなく、頭痛や全身のだるさ、肩凝り、動悸、食欲不振など体の不調を伴い、独特の絶望感は死によって問題を解決しようとする自己否定へつながるといわれる。原因は、ストレスなどによって脳内の神経伝達物質の働きが悪くなって起こるとされ、休養と適切な治療で「治る病気」である。誤解されやすいのは、個人的な意志の弱さや怠けで起きる病気ではないこと。いちばんの問題点は、治る病気でありながら、病気とは気づかず、また精神科受診への偏見が根強く、うつ病の人の半数以上が適切な治療を受けていないことだ。 |

徳島生まれの山本深雪さんは、剣山のふもとの豊かな自然の中でのびのびと育った。両親との関係を絶つ決心をしたのは大学進学の時。共に教師で、山本さんにも教職に就くことを強く望んだ両親は、彼女が目指す薬学の道は頑に認めようとしなかったのである。以来、富山の大学に奨学金のみで進み、その地で10年ほど暮らした。
身体の異変を感じるようになったのは、大学入学後、結婚し、出産も経験した20歳の頃。生来の生真面目な性分と、体力に自信があったことが却ってマイナスになったのかもしれない。それまでは無理をしても何とかなるという気持ちが強かったのに、世の中には何とかならないことが多すぎた。それに気づいた時、現実を受け入れにくい自分がいたという。
最初に表れた症状は胃潰瘍。治療を終えた医者からは「くよくよ悩まず、朝昼晩3食きちんと食べて、規則正しい暮らができれば病気は治りますよ」との言葉。しかし、「食欲がない時にはきちんと食べることなんて物理的にできない。それができたら悩まないよな」という思いが強く、その複雑な思いを医者に伝えると、心療内科を勧められた。
「その当時の私はとても生意気で、心を他人に治療してもらうことなんてできるの?それほど弱い私だったの?という気持ちが強く、そんな自分を認めたくなくて後ずさりばかりしていました」
23歳で生理が止まり、耳鳴りやめまいが続いた。熟睡感がなく、食欲もまったくない日々。体重が1カ月で10キロも減り、産婦人科に行くと「更年期症状です」と診断された。だが、どうする術もなかった。
「ただ、大学を卒業するにあたって自分がどう生きていいか分からない。社会への出方が分からなかった」と振り返る。
その年のクリスマスのことだ。
「車で家に帰る途中に気持ちがなえてきて、前にも後ろにも進めないと頭が考えるようになり、身体も反応してその場で動けなくなった。それも、踏み切りの上で・・・。段々と近づいてくる列車の光は見えても、全然リアリティーがなく、恐怖感もなかった・・・」
カーブの遠心力で列車に車ごと飛ばされた。翌日、気がついた時には外科病棟のベッドの上。新聞では重体と報道され、頭からの出血などもあったが、奇跡的にも膝の神経が切れ、顔や手にガラスでの切り傷が残った程度。松葉杖でのリハビリ期間は、「本当にゆったりしてこんな時間もあるのかとすごく穏やかな気持ちになれた」と話す。
「病人になるというのはこういうことなのか。三食の用意をはじめ、〜をしなきゃあいけない生活から逃避できて、病人になるという感覚が少しづつでも自分で認められるようになった気がしました」
退院した後、友だちに精神科へ連れて行かれた。医師を前に、何も言いたいことはなかったという山本さん。友人の説明を聞いた医師は「自我の崩壊ですなあ」と冷たいひと言。あまりに無礼な印象で二度と行く気にならず、もう少し話ができやすくて薬の量も少なく、相性の合う医者を探したいと、見つけたのが心療内科と皮膚科を併設する病院。そこで、「うつ状態だが、うまくすれば3カ月くらいで治ります」と診断された。その時点から神安定剤と睡眠前の薬を飲み続けてきた。

 その後、うつ病による「就労不能」の診断書が出され、5年間生活保護を受けた。同じ病気をかかえる友人らと三軒長家で共に暮らしたが、心の病気ということだけで周囲から特別視され、近所で不審火が続けば疑われるなど、不安がられる日々が続いた。そして、根拠のない立ち退きを迫られる結果に。そうした重圧は仲間の薬の量を増やし、薬の副作用を引き出す要因ともなった。さらには、買物や外出時に知らない人に尾行されるといった不愉快な行動にもつながった。 その後、うつ病による「就労不能」の診断書が出され、5年間生活保護を受けた。同じ病気をかかえる友人らと三軒長家で共に暮らしたが、心の病気ということだけで周囲から特別視され、近所で不審火が続けば疑われるなど、不安がられる日々が続いた。そして、根拠のない立ち退きを迫られる結果に。そうした重圧は仲間の薬の量を増やし、薬の副作用を引き出す要因ともなった。さらには、買物や外出時に知らない人に尾行されるといった不愉快な行動にもつながった。
「その地域では、精神病で養生する“土地の人間ではない者”に対して許容する力はまったくなく、施設や病院に入るのが当たり前という風潮も感じました。子どもがいたからどうにか生きられたのかもしれません。とにかく、いちばんの問題は自分の人生がよく分からないことでした」
その頃、親や友人から「なぜこんな病気になったか原因を探せ」とよく言われた。今にして思えば、それは周りにいる人たちの問題だったのだという山本さん。当の本人は、ただしんどくて頭が働かず、何もする気が起こらない。外に出る気力もないだけだった。
「その気持ちが周りの人にはなかなか認められない。そういう会話をすることが苦痛だったのに、周りからは逃げてると言われるばかり。そのしんどさを理屈抜きで共感しあえるのは同じ病気の人しかいませんでした」
もう一人では子育てができないと感じるようになったのが、29歳の後半から。ひょんなことから、別れた夫側の義母にお世話になることになる。実家と縁を切っていたこと、孫がいたこと、しかも義母は元夫にとって2度目の母で血縁関係がなかったことが幸いした。義母は一緒に病院を探し、通院も付き添ってくれたのだ。
「今思えば私は女性で、家でゆっくり養生できたのが良かった。もし男性だったらどうだったか。そういう意味では恵まれていました」
義母とともに行った病院で初めて医師から指摘されたのが薬の量。「このままの量を服用し続けると、自分のしたい暮らしができなくなる」と半分に減らすことを勧められた。人間に出していい1日の極量を越え、多剤大量投与となっていたのだ。極量を超えると本来期待する効果より副作用のほうが出てしまうのだが、「いくら自分が専門家ではあっても、その時期には極量のことなど考える力はなかった」と山本さん。

 少し落ち着いた頃から子どものために働かなければと、家で縫製のミシン作業を始めたが、1カ月どんなに頑張っても収入は2万円程度。外出に慣れる時間を少しずつ増やし、職業安定所にも足をのばすようにした。自分らしく生きるために頼りになるのは法律しかないとの思いから、法律事務所の事務職として勤務することを決断。「最初はかなり辛く、断崖絶壁に立たされた感じだった」というが、なんとか8年間勤め続けた。その間に、死刑判決を受け獄中で発病する人や拘禁症状で医療を望む人たちとの手紙のやり取りを弁護士を介してくり返すようになったいた。そして、1985年に設立された「精神医療人権センター」の活動に参加するようになっていく。 少し落ち着いた頃から子どものために働かなければと、家で縫製のミシン作業を始めたが、1カ月どんなに頑張っても収入は2万円程度。外出に慣れる時間を少しずつ増やし、職業安定所にも足をのばすようにした。自分らしく生きるために頼りになるのは法律しかないとの思いから、法律事務所の事務職として勤務することを決断。「最初はかなり辛く、断崖絶壁に立たされた感じだった」というが、なんとか8年間勤め続けた。その間に、死刑判決を受け獄中で発病する人や拘禁症状で医療を望む人たちとの手紙のやり取りを弁護士を介してくり返すようになったいた。そして、1985年に設立された「精神医療人権センター」の活動に参加するようになっていく。
私生活では34歳で2度目の結婚をし、38歳の時に離婚。法律事務所を退職、そして入院。退院後は、身体に障害のある人たちのたまり場で時間を過ごすようになった。手話で会話する人々の中で、カタチは違ってもコミュニケーションの大切さを痛感する。
「自分にとって、それまで欠けていたコミュニケーションを自分なりの方法で始めようという思いから、積極的に人権センターと関わるようになっていきました」
40代になって、精神的に楽になった時期でもある。ジタバタしてもどうにもならないと思えるようになったというのだ。交通事故で一度終わったはずの人生、その残りをどうしていけばいいのか考えられるようにもなり、社会に出たことで小さな自信もついた。
精神医療人権センターの一員として積極的に病院の精神科病棟に出向き、自分なりの言葉で患者さんたちに話しかけるようになった。かつて自分が辛かった時期に先輩たちがやさしくかけてくれた言葉を思い出しながら。そうした入院患者の生の声をコツコツと聞く作業は、退院患者や家族からも多くの情報を集める結果となる。そして、劣悪な医療実態が公となって廃院にまで追い込まれた「大和川病院事件」にまでつながっていったのである。その間にも精神に障害のある人の人権について大阪府との協議は重ねられ、その波は行政まで動かすことになったのである。
|


