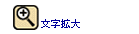
もしあなたが、あるいは、あなたの家族が重い病気にかかったとしたらどうしますか。初対面の医師にすべてを任せられますか。多分、ほとんどの人はうろたえながら、それでも病院側の説明を懸命に聞き、「最善を尽くします」という医師にすべてを託すことになるのでしょう。そんな時に決まってふつふつと湧き出てくるのが、主治医に聞きたいけれど気後れして聞けない不安や心配事の数々。そうした思いを気軽に相談できる専門医がいたら、どんなに救われるかしれません。ホスピス医・森津純子さん(37歳)が、東京の茗荷谷で開業する「ひまわりクリニック」は、まさにそれ。ガンのカウンセリングを主とした小さな病院ですが、病院と患者や家族の橋渡し役をしてくれる希少な存在です。ホスピス医として数多くの「死の瞬間」を見つめてきた森津さんの言葉は、不思議なくらい肩の力が抜けていて、それでいて力強い。「死は決して絶望だけではなく、小さな希望の光も秘めている」と、やすらぎのメッセージを贈ってくれるのです。
 |
 |
「幸せに死ねる方法が、今の世の中にないのかな」と思ったのが、ホスピス医になるきっかけでした。これまでたくさんの「死」に立ち会ってきて感じるのは、死って特別のことじゃない。人間界では、「誕生」が当然のごとく起こるように、「死ぬ」ことも当然あって、自然なことなんです。
でも、新米医者だった私が病院で見たのは、たくさんの管をつけ、機械に生かされている患者たち。一般的に医者は治すことだけを考えて、ガンの末期になっても抗ガン剤などを使うため、苦しみにのたうちまわりながら体中管だらけになって亡くなっていく人たちでした。こんなにならなきゃ人間は死ねないのかと、悲しくなってしまったのです。ガンのような病気にかかった時、最後まで治したいと思う人もいるけれど、治らないのだったら、なるべく苦しい思いをしないで、残された時間を気持ち良く過ごしたいという考え方はいけないのかなと思うようになりました。
 そんな時期に、ホスピス医の存在を知ったのです。最初は白黒をはっきりさせたい性格から外科医の道を選んでいましたが、急遽、方向転換。医者になって3年目の春、ホスピス病棟を備えた北海道の病院に、そして、翌年の92年には、
新潟県の長岡西病院に日本初の※仏教ホスピス(全国で9つ目の病院、93年3月認可)の医長として出向していました。
そんな時期に、ホスピス医の存在を知ったのです。最初は白黒をはっきりさせたい性格から外科医の道を選んでいましたが、急遽、方向転換。医者になって3年目の春、ホスピス病棟を備えた北海道の病院に、そして、翌年の92年には、
新潟県の長岡西病院に日本初の※仏教ホスピス(全国で9つ目の病院、93年3月認可)の医長として出向していました。
ホスピスとは、ラテン語の「ホスピティウム」(温かいもてなし、宿泊所の意)に語源をもつ言葉で、主にガンやエイズ、その他、根治することが困難な病気にかかった患者が入る施設で、積極的な治療(放射線、抗ガン剤、手術)をせずに、身体と心の苦痛を和らげる治療を中心に行う所です。日本で普及し始めたのは、ここ数年。ホスピス医としても特別の研修項目はなく、薬の使い方や技術的なことは海外のホスピスで勉強してきた人たちから学ぶ他、どういう形で運営していき、どう患者さんを診ていくかはほとんど経験からの独学でした。しかし、紆余曲折を経てたどり着いたホスピスの仕事は、私にとっては天職だった。出会った多くの患者さんから、さまざまな人生を教わりました。



