関東大震災時の朝鮮人虐殺は「今」につながるレイシズムだ 加藤直樹さん
2015/01/29
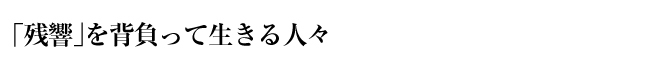
| 『風来記 わが昭和史(1)青春の巻』(保阪正康著、平凡社)を出典に、ノンフィクション作家・保阪正康さんの父のことが綴られている。 人づきあいを好まず、不信の目で人を見る世界観を持つ父に反発した。父が余命6カ月の宣告を受けた75歳のとき、保阪さんに「これから言うことはよく聞いてほしい。あなたに伝えることで私もやっと背負っている重荷から解放されることになる」と語ったのは、関東大震災で瓦礫となった横浜の街で「あまりにもひどい光景」に居合わせたからだ。 路上に倒れた青年に井戸から水を汲んで与えた次の瞬間、背後から5、6人の若者が「中国人に水なんか飲ませるな」と怒鳴り、その留学生を棒でたたき、小刀で刺して殺してしまった。「あのときから横浜には二度と足を踏み入れていない。なぜなら怖くて怖くて横浜には行けないんだ」 (要約) |
――虐待・虐殺を目の当たりにした衝撃によって、一生消えない心の傷を負った人たちの話も強烈でした。

友人のお父さんに、沖縄出身の人がいました。故郷の人たちからお金を借りて事業を興し、大成功したのに、最後に大散財して借金の山を残して亡くなった。どこか、破滅的なところがあったんですね。彼がなぜそういう人になったのか。亡くなってから、小さいときに目の前でお母さんを米兵に機銃掃射で殺された経験があったことを知りました。
その話を聞いたのはアフガン戦争の頃でした。僕はテレビでアフガン戦争の映像を見るたびに、この爆撃の下で、友人のお父さんのように心の傷を一生背負う子どもたちがたくさん生み出されつつあるのだと思わずにはいられなかった。
歴史にアプローチするときに欠けがちなのは、そんなふうに、その後も長く虐殺や戦争の残響を背負って生きる人々がいるという視点。残響がその後の社会にずっと響いていくという視点です。先の沖縄の友人のお父さんの例でいうと、次の代にまで影響を与えるわけです。そういうことが関東大震災についても言えるはずだと思っていたときに、保阪さんのお父さんのエピソードを知ったんです。
――トラウマになった、ということですよね?
本に書きませんでしたが、関東大震災時に荒川・四ツ木で死体が薪のように積まれているのを見た朝鮮人労働者は、その後、一生、夜中にうなされ続けたということを、奥さんが記録映画の中で語っています。なだめようとした奥さんに、立ち上がって首を絞めたそうです。
少女時代に震災を経験した在日のお婆さんについての記事を読んだことがあります。彼女は大家さんにかくまわれていたのですが、建物の外が騒然としていたとき、お父さんの友人が「ちゃんと話せば大丈夫だ」と外に出ていった。その後、外から「わー」と叫ぶ声が聞こえ、窓から覗くと、その人の首を竹槍の先に突き刺して、自警団が歩き去るのを見てしまったのです。娘さんの言葉として書いてあったのは、彼女は年をとってから夜中に「地震が来る」と言って起き出したりしていたそうです。また、「日本人を怒らせると殺される」とも言っていたとも。
恐怖の記憶が生涯消えないんですね。
直接の経験者ではなくても、在日の間では、関東大震災の経験というのは差別の先にある最悪の事態として、恐怖とともに語り継がれてきました。石原都知事の三国人発言を聞き、恐怖を覚えた人も大勢いたと思います。
――まるで、傷口に塩を塗るような発言でした。
最近のことですが、在日の実業家に「この二、三年、いつかまた関東大震災のようなことがあるのではと感じて恐い」と真顔で打ち明けられたことがあります。温厚な方で、決して大げさなことを言うような人ではありません。日本人には見えにくいけど、在日の人々が肌で感じている危うさがあるわけです。
問題が根深いのは、虐殺現場の当事者一人ひとりに、恐怖の記憶がつきまとうのは個人のトラウマですけど、広く社会もトラウマを抱えているということです。
トラウマという意味では、関東大震災の7年後、1930年に北伊豆地震が起きたときも朝鮮人暴動発言が流れました。災害の後の非常時に外国人が暴れ出す、というイメージが繰り返しているんです。これも、ある種社会のトラウマですね。
災害に乗じて外国人が暴れるというイメージは、関東大震災時の民族差別的なデマが基点だったわけです。デマであったことが分かったあとも、外国人の暴動という強烈なイメージはきちんと清算されずに来てしまった。「あのときの誤り」、朝鮮人虐殺という誤りをきちんと清算しなかった結果です。その流れの上に、90年後の我々も生きているんですよ。
――「あのときの誤り」を胆に命じた方として本に登場したのが、千田是也さんですね?
ええ。もうお亡くなりになっていますが、演劇の世界の大物で、戦前はプロレタリア演劇もやっていた方です。
千駄ヶ谷で朝鮮人と間違われて殺されかけた経験から「千駄ヶ谷のコレヤン(Korean)」の意味で、千田是也という芸名を名乗ったこと自体は、かなり知られた話です。でも、そこにどういう気持ちが込められているかは、意外と知られていない。
実は、千田是也は「自分も加害者になっていたかもしれない」という自戒を込めて名乗っていたんです。
関東大震災の翌日の夜、彼は、自警団が朝鮮人を追う「鮮人だ、鮮人だ!」という叫び声を聞き、はさみ撃ちにしてやろうと、自分も走った。ところが、ぶつかった相手が自警団で、彼の方が朝鮮人だと思われて取り囲まれ、「叩き殺すぞ」とこずかれる。本名を名乗り、「早稲田の学生です」と学生証を見せても聞き入れられない。自警団の中に偶然近所の人がいたために助かった......。
「自分が殺されかけたから」ではなく、「自分も朝鮮人を殺したかもしれない側だったから」。その自戒からの芸名だったんです。
――「殺されかけたから」と「殺したかもしれない側だったから」は、意味が全然違います。
不十分にしか伝わっていない彼の真意を伝えたかった。
そういう意味でも、僕がやったのは、編集みたいなことです。
証言にしても新聞資料にしても、大量にありました。それらは、執念で朝鮮人虐殺を追究してきた少数の学者たちが、流言はどのように広まったか、あるいは、政府がどう関与したかといったことを、学問的なアプローチを通じて明らかにするために集めたものであるわけです。
それに対して、僕は、あの出来事はなんだったんだろう、何を学ぶべきなんだろうという素人の問題意識でそれらを読み、ひっかかってくるものを選んで、この本を編んだわけです。
――メディアが煽っていたと検証されていました。
日本の新聞は、三一運動(1919年3月1日に日本統治時代の朝鮮で起こった独立運動)以降ずっと「朝鮮人は恐ろしい」と報じています。
たとえばある論文で紹介されていた震災前年の記事ですが、「丹波の水源地の施設で、設備をハンマーか何かで叩いている人影があったので職員が駆けつけると、怪しい朝鮮人風の男が逃げ去った」というものがありました。「朝鮮人風」とはどういうことか。なぜ彼が朝鮮人かもしれないと思ったのか。何の説明もない。朝鮮人は何をするか分からず恐ろしいと連想させようとする、おかしな記事です。気になるのは、すでに「水源」に毒を入れようとしていると匂わせていることです。
三一運動以降の朝鮮人の独立運動には一部に武装闘争も含まれていましたが、新聞はそれらを常に誇張し、「爆弾」「短銃」「陰謀」といった文字と共に「不逞鮮人」という憎しみがこもった文字を乱発します。関東大震災の日の東京朝日新聞朝刊にも「怪鮮人3名捕はる/陰謀団一味か」という見出しが躍っているんですよ。そして、大震災が起き、そのさなかにも新聞はデマをばんばん伝え続けた......。
――それから90年の今、インターネットにはヘイトの書き込みが横行しているわけですよね?
本書を読んだ人からも、そこに恐怖を感じていると感想をもらいます。
僕がそもそも関東大震災時の朝鮮人虐殺に関心を持ったきっかけが石原都知事の三国人発言で、災害に関する社会学関係の本を読んで、ありもしない恐怖が外国人なりマイノリティーなりを敵視する流言をつくって、悲惨な二次災害を起こすということがよくあったと分かったと先ほど言いました。
第1次大戦中にカナダで国会議事堂が焼けたんですが、対戦国のドイツ人が放火したに違いないと、国中でドイツ系カナダ人やドイツ人が警察に連行されるという出来事があった。実際は単なる失火でした。
中世のフランスでペストがはやったときに、ユダヤ人が毒を入れたせいだと流言が広まり、大量にユダヤ人が虐殺された。
1900年代初めのサンフランシスコで、空き巣が横行しているという流言を市長が信じて、軍に出動を要請。軍は動くものは撃て、という命令を出した。倒壊した自分の家に荷物をとりにきた主婦まで撃たれた事件もあったんです。
新しいところでは、2005年にニューオーリンズをハリケーン・カトリーナが直撃したとき、強盗が横行している、避難所はギャングに支配されているなどと流言が広がり、州知事や市長らがこれを事実であるかのように宣伝した。メディアは「無法地帯ニューオーリンズ」と扇情的な報道をしました。その結果、黒人男性が白人の「自警団」に撃たれる事件が頻発したんですよ。
――流言と誤ったメディア報道を行政がつないだということでしょうか。
そうです。調べていくと、レイシズムの流言が流れて、行政がそれに加担し、広げてしまうというパターンがあることが見えてきました。僕は、石原都知事の三国人発言は災害時に起こりうる最悪のパターンにつながる。この人が都知事でいる間に東京で大きな地震が起きたら、怖いと思った。
当時そんなふうに周りの友人たちに伝えても、皆からぴんとこないと言われたんですよ。ところが、この本を出した後、ツイッターに「これは90年前のことじゃない、今のことだ」と書き込みもあり、分かってもらえたんだと。ネット上の議論の中に「そういうやり方をしてたら、自警団の二の舞だ」「おまえのやってることは朝鮮人虐殺の元になった流言を流しているのと同じだ」などというのもあった。
この本が現代のことを考える補助線になればと思っていましたので、そのことが読者に伝わったとすればうれしいですね。
――最後に。出版後、想定外のことはありましたか?
在日の人の反応でハッとさせられたのは、ある講演会で話した後、おばあさんがやって来て、「私の祖父はあのとき、鳶口で頭を刺された。命はとりとめたが、朝鮮に帰った」と語ったこと。
もう一つは、在日の若い人から「朝鮮人が『助けてもらった』のではなく、自ら闘って抵抗した記録はないのか」と聞かれたこと。その場では咄嗟にとんちんかんなことを答えてしまい、ずっとひっかかっているんです。
ネットの書き込みに、「祖父は川崎の飯場にいて、親方に守ってもらって助かった」と記した人が、「しかし、何も悪いことをしていないのに、かくまわれなきゃいけない人の苦々しさが分かるか」と重ねて書いていたのも、意表を突かれました。
「正直、僕は頭を鳶口で刺されるのが怖い」という在日の若者の書き込みもあった。恐くてこの本が読めないと。殺される側の恐怖というものを、どれくらい感じているのかと問われたような気がします。
やはり、僕が書くものはどうしても日本人の視点になっていると思います。こうした反応から、書くときには考えていなかったそれらのことを、今、考えさせられています。
(2014年12月1日インタビュー 取材・構成/井上理津子)
加藤直樹(かとう・なおき)さん
1967年東京都生まれ。出版社勤務を経てフリーランスに。近現代史上の人物論を「社会新報」他の媒体に執筆。「九月、東京の路上で」が初の著書。


