「結婚差別」を人権の問題として取り組む 齋藤直子さん
2018/08/10

被差別部落出身であることを理由に、親などから交際や結婚を反対される。「子どもは産むな」と言われる。「親子の縁を切る」と迫られる。そんなことが身近で起きた時、あるいは自分が直面した時、あなたはどうしますか?
「結婚差別」を経験した人たちの聞き取りや相談を重ねながら、社会学の視点で分析と考察をした『結婚差別の社会学』の著者、齋藤直子さん。取り組みから見えてきたことや伝えたいことなどを話していただきました。
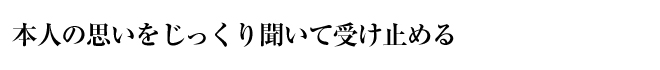
――齋藤さんが結婚差別に関心をもたれたきっかけは何ですか?
大阪府が2000年に「同和問題の解決に向けた実態等調査」をした時、聞き取りのチームに参加したんです。被差別体験を語ってもよいという方に、お話を伺いました。40人ぐらいに語っていただいたなかで、結婚差別の体験がすごく多かったんですよ。それまで部落問題について聞き取りはしていましたが、結婚差別をテーマにしていたわけではなかったので、「こんなに多いんだ」と驚きました。
その後、ネット上で結婚差別の相談を専門に受けている「ネットワークKakekomi寺(※)のメンバーである大賀喜子さんから「一緒にやりませんか」と声をかけられたりして。自分の意思で選んだというより、流れがあったというか、必然としてやってる感じです。
実態調査での聞き取りにも驚きましたが、Kakekomi寺での相談は、さらに驚くこともありました。Kakekomi寺では部落出身者だけでなく、部落外の人もけっこう来るんです。その相談のなかで、家庭内で何を話されているのかを聞くと、すごい(差別的な内容で)・・・。「ああ、こうやって差別は作られてるんだな」と。
――部落外出身者でKakekomi寺に相談に来られる人は、どういうルートでつながったのでしょうか。
創立メンバーは長年、それぞれの地域(被差別部落)で個人的に相談を受けてきました。だけど地域に住んでいない部落出身者もいるので、インターネットを通じて広く呼びかけていくことにされたんですね。すると、ネット検索で見つけたという人が何人も連絡をとってきたそうです。やっぱり今は、悩んだ時にはネット検索をするという人が多いんですね。
また、メンバーたちはこれまでの経験から、裁判や糾弾、地元での相談といったこと以外に、もっと多様な選択肢が必要だという思いから、Kakekomi寺をはじめたそうです。
ただ、今はネガティブな情報が上位に上がってくることが多いんです。すると「やっぱり(この結婚は)ダメなのかな」と思ってしまう。だからできるだけポジティブというか、正しい知識や情報が上位に上がってくるようにしなければとすごく思いますね。
――裁判では救われない部分とは、具体的にはどういうことですか?
大賀さんの受け売りなんですけど、民事訴訟はどうしても被害をお金に換算することになります。その人自身の心情を汲み取って、理解して、癒していくというところが重要だけど、今まではそこが全然足りていなかった。もちろん、地元でそういった精神的ケアをされてきた人はたくさんいたと思います。Kakekomi寺ではそれをもっと広い範囲でやりたいと。だから、悩んでいる人の話をよく聞くということを一番大事にされています。
結婚差別というのは、それだけでも耐え難いことですが、今後の人生の見通しにも影響が出てしまいます。この社会では、女性は男性に比べて、一定の年齢になると、結婚の機会を得ることが難しくなっていきます。「30歳までに結婚したい」「30代半ばまでに子どもが欲しい」といった人生設計があったとして、20代後半で結婚差別に遭ったとします。結婚差別によって、結婚の時期が大幅に遅れるかもしれません。場合によっては別れてしまって、別の相手といちから恋愛をはじめないといけないかもしれません。このあと出会いがある保証もありません。これは、部落の女性も、部落外の女性も経験することだと思います。そういった不安を抱えないといけないのも結婚差別のしんどさのひとつだと思います。
実際、相談を受けていると「こんな差別をするような人たちはもういいです。気持ちを切り替えて、新しい出会いを求めていきたい」と言う人もいます。女性個人の問題ではなく、まだまだ結婚のプレッシャーが女性に強くかかる社会であるのを感じますね。
Kakekomi寺の相談は、部落出身の方も部落外の方も両方来られますが、いずれの場合も女性が多いです。相談は、部落問題に限らず、一女性としての気持ちをじっくり聞かせてもらうことが必要なのかなと思います。
――差別によって傷ついたり怒りを抱えたりすると、冷静に考えられなくなったり、やみくもに怒りをぶつけたくなることがあります。でも時間をかけて話を聞いてもらうなかで少し癒されて、また考える力を取り戻すというところがありますね。
そうですね。そして結論は本人が出されます。
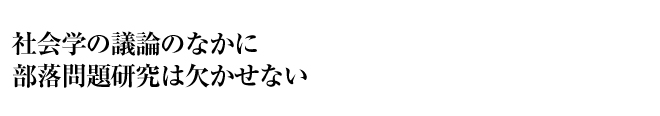

――調査や相談を通じてていねいに聞き取ってこられたことを社会学の視点で分析されました。それが『結婚差別の社会学』という本になったわけですが、どんな"読者"を想定されましたか?
もちろん、タイトル通り「社会学」で、一応、学術書として出しました。でも社会学の学術書としてしか読まれなかったら意味ないやんというところもあって。学術書としての水準を目指しつつ、一般読者や悩んでる人に「あ、探していたのはこれや」と手に取ってもらえるにはどうしたらいいのかと悩みました。
学術書というかたちにこだわったのには理由があります。私の専門である家族社会学でもそうですが、教育社会学や都市社会学などでも、部落問題は今まで以上に広く研究されるに値する重要なテーマだと思っています。実際のところ、家族社会学の分野で部落問題を研究している方はごくわずかです。しかし、家族やイエ制度といったものを考えるとき、部落問題は密接に関わってくると思います。結婚差別問題は、まさに家族やイエの問題です。
だから、学術的な理論というところに持っていくことで、部落問題以外の研究をされている方と議論を共有するための基礎資料になることを目指しました。また、若い研究者たちにも、部落問題の研究は面白そうだと思ってほしかったです。そういう仕掛けになればいいなと思いました。
――家制度や家族という点でいうと、今の親子関係が従来とは違う意味で強い結びつきが見られると書かれていたのが印象的でした。
そうですね。聞き取りでも、学生たちと接するなかでも感じたのが、親子関係の"強さ"です。たとえば聞き取りのなかにこんなケースがありました。部落出身者の女性と部落外の男性との間に結婚話が出た時、「親は市会議員だから、君が部落出身だという話は周りには隠しておいてほしい」と言われたんです。後で女性が振り返って「情けない男やなあ、親がおれへんかったら生きていかれへんのかと思った」と話してくれました。その事例を読んだある学生が「親が大事なのは当たり前。親を大事にしていることをどうして責められないといけないのか」と書いてきたんです。
この女性が部落差別を受けたことはすっとばして「親は大切にすべき」という思いが出てくる。驚くと同時に、この論理を切り崩すのはけっこう難しいなと思いました。ただ、その学生のコメントを紹介すると、他の学生から「親に差別はいけないと言うのも(子どもとしての)愛情ではないか」というコメントが出てきて、「なるほどな」と思いました。
――従来の保守的な意識とは違う家族意識みたいなものがある、と。
はい。家父長制的な、上からくるものじゃなくて、単純に「親が好き。だから親が反対するようなことはしたくない」という考えはけっこうありますね。親は一番話を聞いてくれるし、一番いいアドバイスもくれる。友だちや恋人は代わっても親は代えられない。そういう"信念"みたいなものがあるのを感じます。
私ももともと自分の親が大好きでしたが、やっぱり自分が大人になるにつれて、大人の人間同士の対等な関係になる場面があるじゃないですか。自分自身が人生の経験を積む中で、親の言うことはなんでも正しいわけじゃなくて、私の考えとは異なるということも出てきます。親を相対化して見られるようになるというか。関係性は年齢や経験によって変わっていくだろうから、今は「親のアドバイスが一番」「親が好き」一辺倒な若者でも、年齢を重ねるうちに変わっていくだろうから、そのような意見にはあまり悲観はしていませんが。
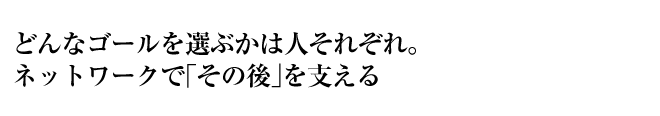
――差別をしてもいいと言う人はあまりいないと思うんです。でも、いざ自分の子どもが部落出身者との結婚を考えたりすると、「差別する気はないけど」と言い訳しながら、「わざわざ苦労するような結婚をしなくても」「きょうだいが差別されるかもしれない」「身内が反対する」などと言い出す事例が多いですよね。 「いざ」という時も、「差別する方が間違っている」というところがぶれないようにいるには、何が必要なのでしょうか。
たとえばセクハラでも、一般的にダメだということになっているのに、身内で起きると急に身内を守る話になったりします。セクハラそのものより、(その人の振る舞いや人格を云々して)「あっちにも責任あるんじゃないの」と言い出すみたいな。結婚差別の聞き取りにも、差別の問題を人格や状況の問題にすり替えるというパターンがいくつもありました。
ふだん「リベラル」を自認している人も、"自分ごと"になると差別する側に引っ張られそうになることってあると思うんです。その時に踏ん張れるかどうかが「知性の力」ではないかと。ふだんからある程度勉強して知識をもっておくことですね。「頭で考えてもしょうがない」という言い方もありますが、私はけっこう勉強が大事だと思っています。自分が問われるような場面になった時、ふだん言ってることと、差別する言い訳を考えてる自分を照らし合せて、「ふだん言ってることと矛盾してるやん」「理屈があわない」と内省することで、そちらに引っ張られることは減るんじゃないでしょうか。
ただ、中には部落に対する拒否感が信念のようになってしまっている人もいます。根拠のない「拒否感」とか「恐怖感」だと思うのですが、いやだとか怖いと思う理由って、合理的に説明できないですよね。そういう感情が湧くのは自分でも制御できない、みたいな。感覚的に強い拒否感をもっている人を論理で変えるのは難しいですよね。
そこを変えることにエネルギーを注ぐよりは、「2人が暮らしていくにはどうするか」と具体的な方策のほうを優先してもいいと思います。聞き取りのなかで教えられましたが、結婚差別をめぐる問題は、いくつかの課題が複合しているので、それぞれを切り分けて、ひとつずつ解決していくことで、道が開けるということもあると思います。
結婚に反対していた人が、差別していたことを反省し謝罪し、仲直りしましたみたいな「完全なストーリー」は、長いスパンをかけてならありうると思いますが、短い期間でそのようにハッピーエンドになるようなことは、あまりないのではないかと思います。だから、そこを目指してしまうと、うまくいかなくて苦しくなることもあるんじゃないかなと思います。
――「親の反対は巧妙だが、それは親が自ら編み出したものではなく、世間に流布する話を取り込んで使っている」とも書かれていて、「なるほど」と思いました。確かに反対の仕方は不思議なほどパターン化していて、逆に言えば"対策"も立てやすいと言えるかもしれません。
一方でカップルのその後は、結婚するにしてもしないにしても多様です。齋藤さんは「結婚前」と「結婚後」とに分けて書かれていましたが、ゴールの形はひとつではないのがわかりました。「結婚したから解決」というわけでもないんですよね。
支援に携わっている人たちから聞いて思ったのは、生活していくという重みです。結婚差別の後に出てくるのは、生活をどうするのかという話。そういう意味ですごいなと思うのは、地道に活動をしてきた人たちのネットワーク力ですね。どこに何があって、誰がどことつながっているか、ビックリするほどよく知っていて、どんどんつなげていくんです。こういう「ハブ」の役割をする人や場所がいくつもあることが大事なんだと思います。
――もうひとつ結婚ということでいえば、この本のテーマは「結婚」そのものではないと感じました。
そうなんです。それはこの本を書く時にものすごく気をつけた部分です。結婚差別を乗り越えるという話をすると、「結婚にこだわらなくてもいいではないか」「結婚という制度自体が差別的だ」という反応もあるかもしれないと予想しながら書きました。イエ制度や結婚制度が差別や抑圧につながると、私も思います。
ただ、この本では、「この人と結婚したい」とカップルが決めたにもかかわらず、親や周囲が反対して、その選択が尊重されないという事態について考える、という限定をつけています。
――結婚差別を切り口にしていますが、「結婚の話」ではなくて「人権の話」なんですよね。ありがとうございました。
(2018年7月インタビュー 取材・構成/社納葉子)
●参考サイト
ネットワークKakekomi寺
『結婚差別の社会学』
剄草書房 2000円+税


