ふらっとへの手紙 関西沖縄文庫 vol.4 金城馨さん
2013/08/07


1972年、沖縄は日本に「復帰」しました。当時、高校生だった私はそれがとてもうれしかった。ずっと「日本人」になりたかったからです。
1歳の時、両親に連れられ、コザ(現在の沖縄市)から兵庫県尼崎市に移り住みました。沖縄人が多く住む地区で、周辺とはあきらかに雰囲気が違っていました。小学校時代、「沖縄からきました」と自己紹介したら「オキナワだ、オキナワだ」とはやされ、沖縄と日本とは「違う」のだと身をもって知らされました。成長するにつれ、豚のエサを集めて回る周囲の大人たちを恥ずかしく思ったりもしました。そして「日本人になりたい」と強く願うようになったのです。「日本人である自分」をつくろうとがんばりながら、なり切れないことにも気付いていて、気持ちはずっと揺れていました。

「復帰」の3年後、沖縄から集団就職で大阪へ出てきた青年たちが中心になって「がじまるの会」が立ち上げられました。就職差別など、まだ沖縄人への差別がはっきりとあるなかで支え合っていくためです。「日本人」と「沖縄人」の間で揺れ動いていた自分に沖縄から出てきたばかりの青年たちがどう見えたか。誤解を怖れずに言えば、「野蛮人」に見えました。当時の自分は「日本人」が上品で高度な文化をもっているようにとらえていたんでしょうね。青年たちの、本音と建前の使い分けなどしない飾らなさや素朴さにとまどいと同時に魅力を感じながらも、20年近く日本で暮らしてきた自分は同じようにはふるまえない。さまざまな感情が入り交じって「野蛮」という感覚が出てきたのだろうと思います。
一方、青年たちから見た私は「日本人」でした。物心つく前からヤマトで暮らしてきたわけですから。私の気持ちの揺れにはまったくおかまいなく、面と向かって「おまえは違う」とひと言で片付けられました。ただ、彼らを批判する気にはなれなかった。沖縄から出てきたばかりで、初めて差別に直面して苦しんでいる彼らと、長い時間のなかで揺れ動いてきた自分とは苦しみの中身が違う。「がじまるの会」の主役は彼らであり、その彼らが私を「日本人」だと感じる現実を受け止めなければいけないと思いました。
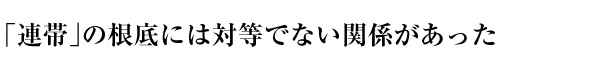
「復帰」後、沖縄の経済はどんどん日本に組み込まれていきます。沖縄海洋博という国家レベルのイベントはまさにその象徴でした。基地問題も含め、そうしたことに抗議する政治的行動を積極的にやりはじめました。「日本人」のさまざまな運動団体と「連帯」することも増えました。ひとつひとつの運動の力は小さいので、連帯していくことが大事だと思っていました。今もそれが間違いだったとは思いませんが、やがて疑問を持ち始めたんですね。沖縄人の自分は日本人のなかではマイノリティです。当時はすでに沖縄人としての個は確立していましたが、その根底には「ヤマトに住んでいるのだからヤマトンチュと共生すべきだ」という自分がいました。今思えば「迎合」です。自分は人権の基本は対等性だと考えていますが、マイノリティ(少数派)がマジョリティ(多数派)と対等な関係をつくるのは大変です。どうしても数の多い方に合わせることになってしまう。私も長い間、日本人の前で本音を言えずにいました。言えば場がしらけたり、反発が返ってくるからです。そして何より排除されるのが怖かったのです。
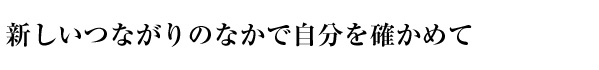
1995年、米兵による少女強姦事件が起こります。被害を受けた少女と家族が声を挙げたことで、沖縄では反基地運動が一気に燃え上がりました。大阪でも「沖縄とともに闘おう」と、準備会に呼ばれました。そこで「沖縄と連帯しよう」「少女の痛みを分かち合おう」という発言が出たんです。自分は思い切って発言しました。「今まで連帯できていなかったからこんなことが起こるんじゃないか」「立場が違うのに"少女の痛みを分かち合う"なんて言うのは傲慢じゃないか」。それは自分自身に対する突きつけでもありました。そして「連帯とはどうあるべきかをもう一度考えよう」という意味で提起したんです。しかしその場での反応は「何を言ってるんだ」と言いたげな薄笑いでした。その後、「連帯を拒否した」「沖縄主義者」「子どもじみている」という非難や決めつけが聞こえてきました。
「もういい」と思いました。ずっと口にできなかった思いを受け止める力がない人たちと一緒にやっていく必要はない。関西沖縄文庫の活動に集中しようと決めました。今の場所に移り、製本関係の仕事を辞めました。いつでも開いているオープンスペースにして、自由に人が訪れ、「沖縄」に触れ、いろいろな人が出会える場にしたかったからです。それまで「連帯」していた人たちからの誹謗中傷は時々聴こえてきます。思わぬ場所で「日本人を嫌いなのか」「連帯を拒否しているのか」と言われることもあります。活動がしにくくなった部分もありますが、逆に若い世代やこれまで接点のなかった人たちとのつながりが生まれました。特に芸術家の人たちは自由な発想でいい刺激をくれます。孤立したことから、自分がおかしいのかと自信をなくしていた時期もあります。しかし芸術家と対等な議論ができることを発見して、自分はこれでいいんだと確かめられました。

関西沖縄文庫という場は自分が変わるために必要でした。多数派にずっと合わせているのは息苦しいことです。非難されても自分に正直でありたかった。今、文庫にはさまざまな立場の若い世代が集まってきます。かつての自分のように、揺れてもいい。そしてバラバラでいい。バラバラだけど固まって刺激しあい、だけど一体化しないのがいいんです。一体化した瞬間、今度は「違い」が出せなくなる。「ここはこうだと思います」と違いを表明すると、「裏切るのか」となる。最初から違いを認め合い、しかし一緒の部分を大事にすればいいんです。そういう意味で、文庫はまとまりのないというか、つかみどころのない「場」にしたかった。「何考えてるのか、ようわからん」と言われたいんです。自分自身も「わからんな、あんたは」と言われると、すごく褒められた気になりますね(笑)。若い人たちにも「仲良くなりすぎないようにしてよ」と言ってます。(談・2013年5月31日)

