ふらっとへの手紙 大阪DARC vol.4 倉田めばさん
2012/12/06


30歳になる頃、薬物中毒で入院した精神科を退院した私は、アルコール依存症の人を対象にしたリハビリ施設に通い始めました。当時はまだ薬物依存症のためのリハビリ施設はありませんでした。
最初は「なんだ、この人たちは」と思っていました。「自分はこの人とは違う」とバカにすることで虚勢を張っていたんですね。
施設の人からは、最初にこう言われました。「薬を使った過去の自分を責めてはダメですよ。それは薬物依存症という病気がさせたことであって、決してあなたの責任ではありません。責任をもちたいと思うなら、クスリをやめ、回復していくことに対してもったらどうですか」。自分をダメな人間だと思い続けていたので、その言葉を聞いてホッとしました。
もうひとつ、ホッとしたことがあります。そこでは毎日ミーティングをおこない、それぞれ自分のことを話すのですが、私は1ヶ月経っても2ヶ月経っても、自分が何枚も仮面をかぶっている感覚がとれなかったんです。ほかの人は正直に話しているのに、自分だけが正直になるまでに時間と距離があるような感じがしたんですね。そのことを相談すると、「そのままでいいんだよ。できるところまで自分を演じ続けるのも回復の過程なんだよ」と言われました。「正直になれ」と言われるに違いないと思いこんでいたので、すごく救われました。その後、仮面をかぶっている感覚は自然にとれていきました。

やがてそこは自分にとってとても落ち着く場所になっていきました。なぜかというと「本音でいられる場所」だったからです。まず薬物依存であることを隠す必要がないし、自分の弱さやずるさをさらけ出してもいい。「こんなところ、二度と来るか!」と言って飛び出したこともありますが、翌日にはまた行きました。ほかに行くところがなかったからです。そんな時もいつものように受け入れてくれました。
依存症ですから、依存できることが大事なんです。そこへ行けば自分の座るところがあり、仲間がいて、一緒にごはんを食べたり遊んだりできる。それをお盆もお正月も関係なく、朝から晩まで毎日やる。そういうことが何よりも救いで、必要でした。
血のつながった家族とは、お金がない時に借りるといった意味での依存はありましたが、施設での人間関係は精神的に依存でき、心がホッとするものでした。感情のもつれもあるのですが、それも含めてそこにいることが心地よかったのです。
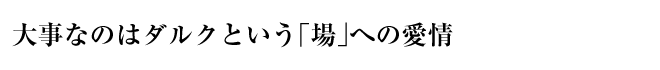
回復が始まってしばらくすると、ダルクの創設者である近藤恒夫さんから「大阪でダルクをやらないか」と言われるようになりました。でも5年ぐらい断り続けていたんです。自分が人を支援するような仕事に向いているとは思えなかったからです。しかし海外の施設を視察して、日本があまりに遅れていることに愕然とし、「人のためじゃなく、自分のためにやればいい」という言葉にも背中を押されて大阪ダルクを立ち上げました。
クスリをやめたばかりとかやめられないという人たちが来たり寝泊まりするわけですから、不安で怖かったです。実際、さまざまなトラブルに巻き込まれてきましたが、医師やカウンセラーなど専門家、家族の人たちに支援してもらいながら乗り切ってきました。一人で抱えこむのが一番まずい。ダルクという場を続けていくために、そして何より自分がつぶれないために、精神的な健康を保つことが大事なんですね。そのために自分の時間を充実させたり、仕事の後はダルクのことを意識的に考えないようにしたりといろいろと工夫しています。
よく自助グループと間違えられるのですが、ダルクはリハビリテーション施設です。ですから実務は効率的にやりますし、ルールを破った人には出て行ってもらわなければなりません。けれど施設としての目標を掲げたことはないし、これからもそうするつもりはありません。依存症とは、マニュアル化された教育とか効率的なスケジュール、組織の機能的なシステムといったものからはずれるために生まれた病気ですから、ダルクでそれをしたらリハビリになりません。
一番大事なのは、私自身も含めスタッフがダルクという場に対する愛情を持ち続けること。それを忘れない限り、社会や制度がいくら変わってもやっていけると思っています。(談)

