ジェンダー
- 2005/03/25
テレビ番組に現れるジェンダーの視点 -
-
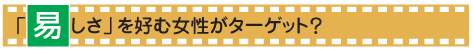
----タレントをコメンテーターに採用する場合、テレビ局側に「この人ならこういう意見を言ってくれるだろう」といった期待があるのは当然でしょうが、露骨に視聴率を取りたいためだろうと思える時など、見ていて違和感がつきまといます。十河さんが、予定調和的な番組の作り方に「ノー」と思うようになったのには、何かきっかけがあったのですか。
私自身、2年前に出産したんですが、その経験や、子どもを預けている保育所で知り合った人たちとの話から、育児中というのは社会の動きに敏感な時期だと分かったんです。外に出る機会が少なく、社会との接点が新聞や雑誌、テレビなどに限られる時期は、逆に、限られた接点から社会的な情報を得ようとするので、政治経済ネタや日々のニュースなどにも知識欲が高い。働いている時期よりも情報に貪欲な人も少なくない、と分かったのがきっかけです。
それに、取材記者として、視聴者の方に街頭インタビューした時などにも、女性の方々に、いろいろなことをものすごくよくご存じの方が多いと思ったのも理由です。こちらの裏側の意図まで読んでおられて、マイクを向けると番組制作者より1枚も2枚も上手の答が返ってきて、こちらが逆に勉強させられる……そんな恥ずかしいこともよくありました。
それなのに、ターゲットを「昼間に家にいる女性」という括りで、易しく、分かりやすく、噛みくだいた内容にしようとしがち……なのはおかしいじゃないかということですね。
----育児休業中に限らず、知識欲が高く、「易しさ」を必要としない女性もいれば、その反対の男性もいますし・・・。
そうなんです。子育て中、介護中---どちらも女性だけがするものではないですけど、女性が多いのが実態ですよね---あるいは、子どもを学校に送り出したあと家にいる主婦の方とか。家にいる女性は「易しい」番組を求めているなどとステレオタイプにとらえずに、番組を作っていきたいと私は思っています。
----ところで、箕面自由学園高校のチアリーディング部の活動を記録した「天国への応援歌~めざせ!日本一のチアリーダー」で、「放送と女性ネットワークin関西」WNB賞の最優秀賞をおとりになりました。あの作品は、どのようにして生まれたのですか。
もともとニュース番組のための撮影に行っていたカメラマンに、「ジャパンカップや高校選手権で優勝したチームが大阪にあるから、一緒に取材に行ってくれないか」と誘われたのがきっかけです。
私は、チアリーディングの大会の取材はしたことがあったのですが、練習の場に行くのはその時が初めて。高校生の部活動の衰退が叫ばれている中、彼女たちが汗を流して一生懸命に練習している姿に、「まだ、こういう子たちもいたんだ」と純粋に感動し、じっくり取材させてもらうことにしました。ニュース放映の後、一本のドキュメントにまとめようと、2001年から2年間、月に2~3回平均のペースで取材に通いました。
----カメラが入ると、高校生たちは変に意識してしまわないものですか?
それが、まったく。大きなカメラを持ち込むので、普通はそれに威圧されないよう、カメラを回しはじめる前に少し時間をおくのですが、彼女たちの場合は自分たちの練習に一生懸命で、最初から私たちがいることに気づかないほどでした。
インタビューは、その都度の判断で行いました。私もスポーツをやっていたので、自分の嗅覚で、現場の“温度”を確かめながら話を聞いていきました。----先に聞いたように、「偏見なし」「予定調和なし」の番組作りだったのですね。
小細工せず、彼女たちのありのままを伝えようと考えました。
インタビューに答えてくれる言葉も、こちらが期待する言葉だけをつないで編集していくというような方法を使わず、ありのままに。そうすることによって、現場の空気を出そうというのをポリシーにしました。
----それによって、何か発見はありましたか。
 チアリーディングの舞台は華やかですから、当初は華やかな演技をテーマに撮ろうと思ったのですけど、練習を見ているうちに、あの華やかな演技の裏側に、上の子に背中に乗られたり、頭を踏んづけられたり、汚い靴を腕にくいこませて支えたりしている子がいる。彼女たちの、怪我をしながら歯を食いしばってがんばる表情を目の当たりにして、その姿をテーマにしたいと考えが変わりました。チアリーディングは組み体操にも似たスポーツなんだというのが、最初の発見でした。
チアリーディングの舞台は華やかですから、当初は華やかな演技をテーマに撮ろうと思ったのですけど、練習を見ているうちに、あの華やかな演技の裏側に、上の子に背中に乗られたり、頭を踏んづけられたり、汚い靴を腕にくいこませて支えたりしている子がいる。彼女たちの、怪我をしながら歯を食いしばってがんばる表情を目の当たりにして、その姿をテーマにしたいと考えが変わりました。チアリーディングは組み体操にも似たスポーツなんだというのが、最初の発見でした。その後も、いろんな発見がありました。
たとえば、ピラミッドの一番下の子は、上の子たちにぐちゃぐちゃに踏み付けられる。イヤだろうなあと思ったんですが、カメラの回っていないところで話を聞いたら、「最初は自分も上になりたいと思ったけど、やっているうちにだんだんやみつきになるんですよ」「上の子がどういう演技をしているのか、後でビデオで見て、全体の形がうまく決まっていたりしたら、すごくうれしいんです」とストレートに言うんです。最初聞いた時は、この子はいい格好をして言っているんじゃないかと思った。でも、それが純粋な気持ちだと分かり、「すごいなあ」「私のほうが濁っていたなあ」と思いました。
----フィルターを通さなかったから、そのテーマが見えてきた、と。
そうですね。支える者と支えられる者というテーマは、あらゆる仕事の中にも家庭生活の中にもある、普遍的なテーマだと思うんです。支える側には最初「なんで私がしんどいことを」という思いがあるかもしれないし、支えられている側は、支える側のそんな思いにプレッシャーを感じてなかなかうまくいかなかったり。
上のポジション、下のポジションがあり、大会に出場できる子とできない子がいるチアの取材で、そういった「支える、支えられる関係」というのが、目に見える形に出てきたんです。 - 関連キーワード:

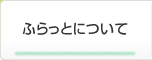
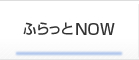



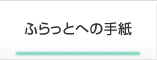


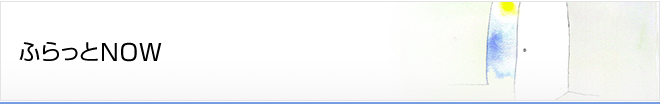
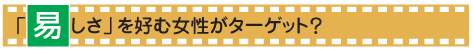


 チアリーディングの舞台は華やかですから、当初は華やかな演技をテーマに撮ろうと思ったのですけど、練習を見ているうちに、あの華やかな演技の裏側に、上の子に背中に乗られたり、頭を踏んづけられたり、汚い靴を腕にくいこませて支えたりしている子がいる。彼女たちの、怪我をしながら歯を食いしばってがんばる表情を目の当たりにして、その姿をテーマにしたいと考えが変わりました。チアリーディングは組み体操にも似たスポーツなんだというのが、最初の発見でした。
チアリーディングの舞台は華やかですから、当初は華やかな演技をテーマに撮ろうと思ったのですけど、練習を見ているうちに、あの華やかな演技の裏側に、上の子に背中に乗られたり、頭を踏んづけられたり、汚い靴を腕にくいこませて支えたりしている子がいる。彼女たちの、怪我をしながら歯を食いしばってがんばる表情を目の当たりにして、その姿をテーマにしたいと考えが変わりました。チアリーディングは組み体操にも似たスポーツなんだというのが、最初の発見でした。