|
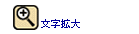
「凶悪犯罪が増え、日本の治安は悪くなってしまった」
凶悪事件や少年犯罪といった言葉がメディアにあふれる中で、多くの人々がこうした固定イメージを持ちつつある。果たしてそれほど治安は悪化しているのだろうか。精緻な犯罪統計分析で知られる龍谷大学法科大学院教授浜井浩一さん(47歳)は、「事実なき神話」だと真っ向から反論する。「治安悪化を前提に、厳罰化や監視強化が進み、社会的弱者を不審者として排除する格差社会を産んでいるのでないか」と。

「統計をきちんと読み解けば、犯罪はそれほど増えていないし、凶悪化もしていない。治安悪化とは言えません」
早稲田大学教育学部で認知心理学を学んだ浜井さんは、国家試験を受けて法務省へ。元官僚であり、心理技官(矯正)として少年院や少年鑑別所、保護観察所などの現場も経験。さらに、国連犯罪司法研究所などへの海外派遣も含め、1996年に異動となった法務総合研究所では4年間犯罪白書を執筆、その後、学者の道を選択するまで、受刑者の人事管理を担う「首席矯正処遇官」として横浜の刑務所職員だったという異色の肩書きの持ち主である。
そもそも浜井さんが治安問題に関心を持ち始めたのは、2000年に矯正処遇官として刑務所に異動してからだ。刑務所は受刑者が増えて、深刻な過剰収容に陥っていた。1997年の神戸連続児童殺傷事件を頂点に、少年による殺人事件が続き、世界一を誇っていた日本の「安全神話」の崩壊報道が一挙に増えていった時期でもある。
「犯罪白書でも、99年から2000年にかけては各種暴力犯罪の認知件数が急増していた時期。治安の悪化から犯罪が増え、受刑者も増えるという当然の現象のようにも思えた。でも、どうもおかしかった。違和感を感じていろいろ調べてみると、ちゃんと働ける受刑者がいないことに気づいたんです」
 もし犯罪の激増が事実なら、刑務所は凶悪犯であふれているはずである。しかし、浜井さんの目の前には、そんな光景はなかった。所内の工場からは、作業を担う受刑者を至急補充してほしいという要請が相次ぎ、担当者に事情を聞くと思いがけない言葉が返ってきた。
もし犯罪の激増が事実なら、刑務所は凶悪犯であふれているはずである。しかし、浜井さんの目の前には、そんな光景はなかった。所内の工場からは、作業を担う受刑者を至急補充してほしいという要請が相次ぎ、担当者に事情を聞くと思いがけない言葉が返ってきた。
「受刑者はいくらでもいますが、まともに作業できる受刑者はほとんどいません。みな老人か、障害者か、病気持ちばかりで・・・」
あらためて所内の状況を見直してみると、増え続ける受刑者のほとんどがハンディキャップを持つ人ばかり。高齢や生活習慣病、手足の麻痺、難聴などの身体障害、知的障害、覚せい剤後遺症による精神障害、外国人であるための言葉の障害等々。いったん出所しても、軽度の知的障害があるうえに高齢で働けなくなり、ホームレスになって生活に困り、ひもじさから再犯してしまうようなケースが後を絶たなかった。
「刑務所勤務で強く感じたことは、社会が不要となった人材を刑務所に捨てているのではないかという思い。私が見た刑務所は、社会的弱者の福祉施設と化していました」
さらに、2000年から急激に増加している認知件数の増え方も不自然だった。
「認知件数とは警察活動の統計であり、行政的な受理件数です。従って、警察の活動方針が統計に大きな影響を与えます。そこで、警察活動に影響を与える警察トップからの口頭の指示や通達文書を調べてみました」
 大きな要因となっていたのは、99年に起きた「桶川ストーカー事件」だった。犯罪被害をめぐる警察の対応に市民の批判が噴出。同じ時期に神奈川や大阪で警察の不祥事が続いたことで警察改革も進行しており、「告訴や告発は全件受理せよ」といった指示を徹底。「市民の相談事案には積極的に対応すべき」などという通達が出た結果、認知件数の数字は劇的に変化したのである。その結果、余罪捜査をしている余裕がなくなり、検挙率の急な低下につながったという。
大きな要因となっていたのは、99年に起きた「桶川ストーカー事件」だった。犯罪被害をめぐる警察の対応に市民の批判が噴出。同じ時期に神奈川や大阪で警察の不祥事が続いたことで警察改革も進行しており、「告訴や告発は全件受理せよ」といった指示を徹底。「市民の相談事案には積極的に対応すべき」などという通達が出た結果、認知件数の数字は劇的に変化したのである。その結果、余罪捜査をしている余裕がなくなり、検挙率の急な低下につながったという。
客観的統計によれば、殺人、暴行などの犯罪はどちらかというと減少傾向にあり、治安悪化は認められないという結論となった。逆に、古き良き時代としてノスタルジーを駆り立てられる「三丁目の夕日」時代、昭和30年代が少年による事件が戦後最も多かった時期なのである。そして、少年犯罪が起きるたびに枕詞のように使われる「非行の低年齢化」も統計的な根拠はなく、非行自体は減少し、高年齢化(10代で)しているのが現実である。
|


