|
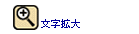


―――最初に、子どもの問題に関わるようになられたきっかけを教えてください。
もともと、子どもや人と接するのが好きなのですが、今の仕事に行き着くまでには紆余曲折があります。進路を考え始めた10代の頃から、人が生まれ育つなかでどのように人格形成され、それが人生にどう影響するのかということにとても関心がありました。その時点では幼児期が重要なのではと思って幼児教育を専攻し、その後、幼稚園の先生になりました。ところが幼児期はとても重要なんですが、幼児期以降の変化と成長を知りたい私にとって幼稚園のなかで関われることには限界がありました。そんな時、たまたま募集していた女子少年院の法務教官に応募したのです。
女子少年院には、事件を起こした14歳から19歳までの少女が入ってきます。彼女たちと接するなかで、その壮絶な人生に衝撃を受けると同時に、育った環境がその人の人生にいかに大きな影響を及ぼすかを目の当たりにしました。わたしの想像などはるかに及ばない現実がありました。事件を起こした子どもたちは育ってくる過程で、心にさまざまな傷を負っています。そこから立ち直りを図るのですが、一人の子を「もう二度と帰ってきてはダメよ」と社会に送り出しても、その日のうちにまた同じような傷をもった子が入ってくる。彼女たちが吐き出してくれた、非行に至る背景や心の傷、そこから知りえたものをを広く伝えていかなければ、この不幸な連鎖は止められないのではないかと考えたのです。そして法務教官を辞め、執筆などを通じて社会に伝える活動などをしていたところ、大阪府の公立小中学校で子どもたちと関わる機会をいただきました。今、育っているさなかでしんどい思いをしている子どもたちに、何か手当てができればという思いで関わっています。
―――10代の子どもたちによる事件が起こるたびに、おとなたちは衝撃を受け、理由や原因を知ろうとします。けれども結局は明確な理由も原因も見つけることができず、「心の闇」と表現されます。実際に事件を起こした子どもたちと接して、理由や原因がわかりましたか?
少年と出会う時、「なぜ、こんな事件を起こしてしまったんだろう」「なぜ、ここまで他人も自分も傷つけてしまうんだろう」と思います。少年院のなかでそれをひもといていくのですが、どんな子にも事件を起こすまでにそれなりの背景があることがわかってきます。それぞれにつまずきの時期があり、何らかのサインを必ず出していました。でもそのサインが読み取られず、あるいは無視され抑えつけられ、適切な手当てを受けられないまま成長し、ついには暴力や薬物や売春といった形で傷を表面化させてしまったのだと感じました。
―――長い間の積み重ねが非行や事件につながっているのですね。非行や事件という形で表面化したことだけに目を奪われていると、事件が起きた「理由」はわからないということですか。
そうですね。実は、彼ら自身も最初は自分の飛行の理由をわかっていません。いえ、理由をきかれると「イライラしてたから」「遊びたかったから」などと言いますが、それはまだ彼らの本当の姿ではありません。彼らの真実を理解するには時間がかかります。自分のことを客観的に見られるまでに成長する必要があるのです。
少年たちはこれまで身につけたものをそのまま少年院で再現します。たいへんな経験をしてきているので少年たちの生活では壮絶なバトルが繰り広げられます。そんなトラブルのひとつひとつを丁寧に扱うんですが、たいてい最初は、なぜトラブルになったか理解できないところから始まります。「相手が悪いから、わたしはこうした」と自己正当化する子も多い。ねばり強く話し合い、自分の心を見つめるなかで少しずつ自分のこだわりや歪みが見えてきます。やがてトラブルの意味が理解でき、「いけないことをした」「こうすればよかった」と考えるようになります。ところが、頭では理解できても、身についた価値観や行動や人間関係のつくり方はそう簡単に変えられません。そうやってしょっちゅうトラブルを起こす自分に、彼女たちはだんだん「先生、わたし、小学3年生からやり直したい」「中学2年の1学期に戻りたい」と言うようになります。彼女たちは自分の非行を口では正当化していたけど、本当はそんなふうに生きてきたくはなかったんです。「本当はもっと素直に自分らしく育ちたかった」という痛々しい叫びを、わたしは感じます。
|


