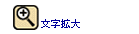
2000年夏の出版以来、ひそかに、しかし着実に反響を呼んでいる一冊の本があります。社会学者である著者の文章はなかなか手強いのですが、緻密で論理的な文から浮かび上がる「『強い』ことが本当にいいのか、『弱い』ままでもいいじゃないか」というメッセージが、強いものに憧れ、強くなろうともがく心を揺り動かします。『自己決定』『自己責任』が叫ばれる時代に、『弱くある自由』を語る著者、立岩真也さん。その真意を2回にわたって話していただきます。
 |
 |
70年代からあった、「弱くある自由」という考え方
・・・まず、『弱くある自由へ』というタイトルにグッときました。とかく『元気な障害者』『がんばってる障害者』を持ち上げる風潮のなかで、「弱いままでいてもいいじゃない」と言ってしまう軟弱さ(笑)。このタイトルに、立岩さんはどんな思いを込められたんですか?
編集者は「売れる本にするために、流行りの『自己決定』という言葉をタイトルに入れましょう」と言ってたんですけど、この本では自己決定そのものについてはそれほど多く触れてないんですね。「それじゃあ『看板に偽りあり』やから、止めよう」と。それで僕が思っていることをそのままタイトルにしたんです。
確かに障害者運動のなかには「自分のしたいこと、やりたいことを主張して実現していこう」という運動ってあったし、あるし、必要だと思うんです。言い換えれば「自分の暮らしのことは自分で決める」、すなわち『自己決定』ということなんでしょうけど。
ただ、そういうことを強力に主張しながら、でももう一方で「少なくとも言葉としては自分の意思を主張できなかったり、しない人もいる。そういう人も含めて考えないと、障害者運動として何か言ったことにはならないんじゃないか」という考え方も、実は障害者運動が始まった1970年代からあったんです。そういう運動の流れがあったことを、知ってる人は知ってるけど、知らない人はまったく知らない。それはやっぱりよくないと思うんですよね。
この歴史的な流れについては最初に出した『生の技法』という本にも書いたんですけど、それを補うことも含めて、「自分を強く主張するのも大事だけど、そうじゃないあり方の人もいるし、そうじゃないあり方もある。そういうことも含めて運動を考えてきた人たちが何をやってきたのか、これから先どうするのか」ということを考えたかったんですよ。
・・・確かに「自分の意思を主張できない人、しない人」、つまり『弱くある自由』も認めようとか、どうするんだという話はあまり聞きませんね。とても大切な視点だと思うんですけど、障害者運動の歴史のなかで、「強くなろう」という主張が目立ち、「そうじゃないあり方だっていいんじゃないか」という声がどんどん小さくなってしまったのはなぜでしょう。
わざわざ僕が調べて書かないといけないぐらいだから、あまり知られていないのは事実です。ただ、昔から「これだけがんばったら、ここまでできる」「これまでできなかった人が、こうしたらできるようになった」という語られ方の方がずっと大きい声だったと思うし、今でもそうだと思う。そういう意味では、昔と比べて『弱くある自由』を認めようという声が小さくなったわけではなくて、むしろ少しずつではあるけど、多くの人に届くようになってきたと感じる部分もあります。



