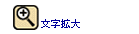
全身の筋肉が少しずつ衰えていくという病気があります。筋ジストロフィー。現在はまだ治療法が見つかっておらず、失われていく機能に対応するのが精一杯というのが実状です。加藤慎大郎くん(14歳)も、その一人。ちょっとした発熱も命取りになり、24時間介護をするお母さんも気が抜けないのですが、ふたりの笑顔に曇りはありません。その笑顔に魅せられるとともに、筋ジストロフィーのことを少しでも多くの人に伝え、治療法の早期発見につなげたいと、写真家の菊池和子さんはしんちゃん親子の写真を撮り続けてきました。死と隣り合わせの日々のなかで、一日をとことん味わい尽くして生きている家族の姿を語っていただきました。

校庭を走り抜ける車椅子
最初はね、しんちゃんではなく、お母さんを撮っていたんです。とても印象的な人だったから。
しんちゃんのいる小学校へ異動してきたばかりの頃、休み時間にお茶を飲みながら何となく校門のほうを見たら、車椅子が見えたのね。「何かな」と思っているうちに、その車椅子がすごい勢いで校門をギュンッと曲がって、ガーッと昇降口へ突進していくのよ。その学校には筋ジストロフィーの子がいるのを聞いてはいたから、その時「あ、しんちゃんだ」とわかりました。車椅子を押していたのが、しんちゃんのお母さんだったのね。
黙って車椅子を押していればそんなにインパクトなかったと思うけど、彼女は校庭で遊んでる子どもたちに「おはようっ」「今日もしんちゃん、元気よ!」って声をかけながら走ってるんです。「車椅子ってあんなに速く走るものなの?」ってビックリしましたよ。
当時、私は教師をしながら、趣味で始めた写真にも力を入れていました。『旬の女』というテーマで、40代以上のイキイキした女性たちを追いかけて撮影していたんです。だからその時のお母さんのすがすがしさに引き込まれてしまって。「イカす女だなあ」と。それで「あなたの写真を撮らせてもらえない?」とお願いしたのが、しんちゃん親子とのおつきあいの始まりです。
37度5分の熱で救急車
 |
|
雨の日の通学路の写真(「しんちゃん」 菊池和子著より)
|
しんちゃんは24時間付き添いが必要だから、お母さんを撮ろうとするとしんちゃんにも目が向くわけです。お母さんのほうは、撮影の日にはシャワー浴びて、しんちゃんとお揃いでおろしたてのTシャツ着て待ってたりするんだけど(笑)、しんちゃんはいつも“そのまんま”なの。表情をつくろうとしないから、とってもいいんですよ。
そうやってしんちゃん親子とつきあっていくなかで、筋ジストロフィーという病気のことがだんだんわかってきたんです。もちろん名前は知っていましたけど、具体的にどういう病気なのかは何も知りませんでした。
筋ジストロフィーというのは、まだ治療法もない難病です。しんちゃんの場合は発病が後天的だったから、青年期を迎える頃にはかなり筋力が衰えて危険な状況になると思われます。筋肉というと、私は腕や足なんかの「骨についている筋肉」をイメージしていたんだけど、とんでもないことだった。身体の内部、心臓や肺や胃や喉、舌なんかも全部、筋肉なのね。それがすべて壊れていくという・・・。
親しくなるにつれて、お母さんは「死はいつも隣りにある。今日はこんなに楽しいけど、明日死ぬかもしれない」なんて言うの。「どういう意味なんだろう?」と思っていたけど、しんちゃんの通院について行ったり、いろんなセミナーに参加して、病気のことを知るにつれて、お母さんの言葉の意味がわかってきました。
たとえば唾液なんかが肺に入っても、肺の筋力が弱いから痰として出せない。それで細菌感染して、死に至るような事態になってしまうんです。
しんちゃんも入院したことがありました。37度5分の熱を出して、救急車で運ばれたそうです。38度になるまで放っておくと片方の肺が真っ白になるんですって。住んでいる調布から新宿にある病院まで、高速を飛ばして20分ほど。「手遅れになる前に入院できたわ。今日は元気になって身体も洗えるようになったから、来てください」ってお母さんから電話があったので、行きました。病院に許可をもらって撮影したんだけど、そういう時に初めて彼の裸を見るわけです。服を着ている彼はとてもかわいいし、車椅子に乗ってはいても“障害者”という気はしなかったんだけど、裸を見れば痩せて、小さくて・・・。6年生だというのに体重が22kgしかないと知った時は衝撃的でした。
 |
|
病院へ向かう電車の中(「しんちゃん」 菊池和子より)
|
そんな時、まだ幼い筋ジスの子どもをもつお母さんのためのセミナーがありました。そこで初めて、筋ジスの治療現場の実情を聞いたんです。難しいことは私にはわからないけれど、結局は筋ジスに取り組もうという研究者がいないんですよね。筋ジスをはじめとする難病は患者数が少ない。だからたとえばガンやエイズに比べると注目度がまったく違うわけです。患者数が少なければ薬が開発されても大きな利益にはならないから、製薬会社も積極的にならない。そんな事情があって、特に若い人のなかで研究者のなり手がいないということを知り、「ああ、これではいけない。しんちゃんの写真を撮って、世の中に働きかけていく仕事をしなくちゃ」とハッキリ思いました。


